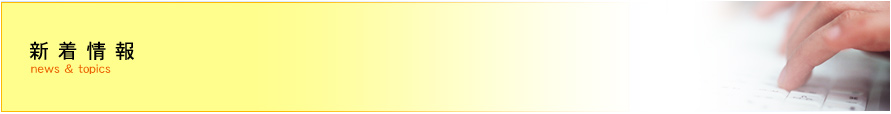第33回松川電氣(株)安全大会開催
2025/06/25

第33回安全大会
皆様こんにちは。
本日は第33回松川電気安全大会にご参加いただき、誠にありがとうございます。
また、日頃より弊社の安全活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、皆様もご存じのように、今年度も厚生労働省では7月1日から1週間、全国安全週間を実施いたします。令和7年度の全国安全週間のスローガンは『多様な仲間と築く安全、未来の職場』です。
今年で98回目を迎える全国安全週間は、労働災害を防止するために、建設業界での自主的な活動の推進と、職場での安全意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的としています。
令和6年度、昨年1年間の労働災害発生状況は、死亡災害228人、休業4日以上の死傷者数は14,000人を下回りました。一方で、高齢労働者に多い転倒や腰痛といった、作業行動に起因する死傷災害、また墜落・転落などの災害は依然として後を絶たない状況にあります。
さらに、新たな労災リスクである熱中症の増加も目立つようになってきています。
わが国では、7月の第1週を全国安全週間としていますが、その1か月前、すなわち6月を「安全週間準備月間」としています。これは他の行事には見られない特徴ですが、安全は計画や準備が大切であることの現れです。
日本には昔から「転ばぬ先の杖」ということわざがあります。転ばないうちにあらかじめ杖を用意しておくこと、つまり何事も用心して準備を怠ってはならないという戒めです。転んでから杖を持ってきても遅いのです。
このように、事故や災害は起こってからでは何をやっても手遅れです。起こさないための準備こそが大切なのです。
「安全対策」と言っても実感がわかず、無関心になりがちです。これこそが一番怖いことです。安全の準備とは、会社がさまざまな安全対策を行い、環境を整備することも重要ですが、最も大切なのは一人ひとりの心の準備です。
「安全作業」に誰もが関心を持ち、注意を怠らないことが何より大切です。
「災害は忘れたころにやってくる」と言いますが、まさにその通りで、安全に対して無関心になった時に事故は発生します。
作業姿勢は安全か、服装は安全か、動作は安全か、足場は安全か、道具は安全か――毎日、それぞれの仕事に応じて安全チェックを行い、習慣づけることが重要です。
そして、新たな労災リスクである熱中症に対しても、適切な対策が求められます。その最大のポイントは、自らの健康管理です。
明日の健康状態を考慮することは、社会人としての鉄則であり、職場の安全は各自の健康管理から始まると言っても過言ではありません。
本日の安全大会は、安全意識の重要性について再確認し、無事故・無災害の職場づくりに向けて、決意を新たにする場です。
今年度も、一人ひとりが安全意識を高めることで、無事故・無災害の職場づくりを実現し、皆様の健康と安全を守り、充実した毎日を積み重ねていくことが、高品質な工事、そして地域への恩返しへとつながると感じております。
どうぞ、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
結びに、本日ご参加の皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げ、挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
令和7年6月25日
代表取締役 小澤 邦比呂

懇親会

第33回安全大会
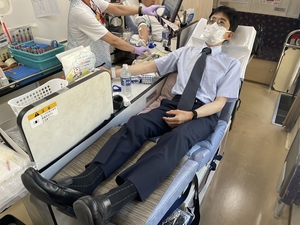
献血の様子